新しい成長分野を模索する日本のエレクトロニクス企業
主任研究員 大平公一郎
- 厳しい状況が続く大手電機各社の業績と日本の電子工業
日本の大手電機8社の業績動向を見ると、ITバブル崩壊から回復・成長を続けた2007年までと2008年の景気悪化以降で方向性に大きな変化が生じている。
2001年から2007年までを見ると、各社ともにいわゆるITバブル崩壊の影響を大きく受けた2001年度に大幅に業績が悪化し、8社中6社が営業赤字に落ち込んだが、2002年度は各社の積極的なリストラの効果もあって業績は急回復を果たす。2003年以降は国内で薄型テレビなどデジタル家電の本格的な普及が始まり、世界では携帯電話やパソコンの出荷数量が年を追って増加した。さらにこれらデジタル製品の普及を受けて半導体や電子部品の需要も拡大が続いたこともあって電機各社の業績回復が進んだ。
また新興国の経済発展が進んだことで電力等の社会インフラ需要が拡大し、世界的な設備投資の盛り上がりもあって重電・産業機械の分野も好調となった。
8社の売上高合計額を見ると、2001年度の43.6兆円を底に2007年度には54兆円と1.23倍の水準まで拡大、営業利益合計額も▲4,197億円から2兆3,901億円に増加し、営業利益率も4.4%まで上昇が続いた。電機各社は海外展開を進めているので各社の業績と日本経済全般の状況は必ずしも決定的なリンクを持つものではないが、日本の名目GDPが2001年の501.7兆円から2007年度の513兆円と2.3%しか成長していないことを考えると2001-2007年度の電機業界は比較的健闘していたといえよう。
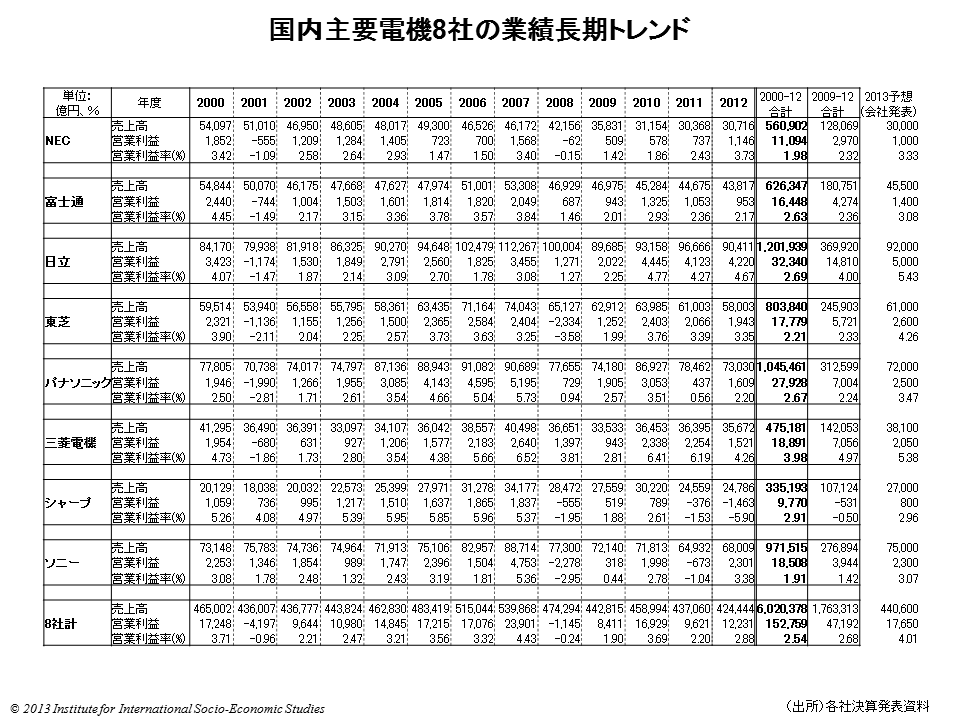
状況が大きく変化したのは2008年度である。リーマンショックに起因する消費者の買い控えや設備投資の縮小が世界中に広がり、その影響から8社のうち4社が営業赤字に落ち込んだ。
8社の売上高合計額は2009年度に44.3兆円とITバブル崩壊後に近い水準まで落ち込んだ後、東日本大震災、タイにおける洪水、欧州債務危機などが立て続けに発生して回復のきっかけがつかめないまま低迷が続き、2012年度は42.4兆円となった。営業利益は2008年度の▲1,145億円から2010年には1兆6,929億円まで戻り、回復基調に戻るかと思われたが2011年度には再び1兆円を下回り、2012年度は1兆2,231億円と低調に終わった。日本の名目GDPは2007年度の513兆円から2012年度の475兆円と7%の減少となったが、8社の売上高合計額は同時期で21%の減少となっており、成長率で下回っている。
低迷の背景には、上述のマクロ経済面の条件悪化の他に、業界個別の要因もある。市場の中心が先進国から新興国に移る中で、日本の電機企業は求められる低価格帯の製品を海外向けに十分に供給できず、また円高も進行し競争力、収益力が悪化する中で、競合他社として台頭してきた韓国・台湾・中国企業にシェアを奪われたことが一因として考えられる。またスマートフォンやタブレット端末といった新しい製品の普及では中核部品・サービスを米国企業に握られ、製品の製造販売でも韓国・中国企業に後れを取ったため、拡大する市場を取り込むことができていないことも大きい。
2008年度以降では個別企業の動きにも差が出ている。比較的業績が堅調なのはHDD事業や薄型テレビ用パネルなど競争が激しくコモディティ化した事業を手放して発電や鉄道など社会インフラ関連事業に注力した産業エレクトロニクス企業群であり、これらの企業は2012年度にかけて順調に利益を回復させている。
一方、厳しい状況にあるのは民生エレクトロニクス企業群であり、主力のデジタル家電が韓国や台湾、中国企業との激しい価格競争にさらされていることに加えて、日本では薄型テレビの市場がアナログ停波前特需の反動で低迷していることも影響している。音楽プレーヤーやデジタルカメラといった製品がスマートフォンに取って代わられていることもボディーブローのように効いていると考えられる。
大手電機の業績以上に大きな変化にさらされているのは日本国内の電子工業生産である。生産実績を見ると、2001年から2008年までは上下はありながらも20兆円近い水準を保って推移してきたが、2009年に大幅に落ち込んだあと回復することができず、2012年では12兆円と2008年以前の水準から6割程度の生産規模に落ち込んでいる。この低下の要因は、円高や国内市場の縮小・海外市場の拡大を背景とした生産の海外移転加速、海外企業との競争激化によるシェアダウン、製品価格の低下などがあげられる。
国内の電子工業を分野別にみると、民生用電子機器は薄型テレビなどデジタル家電の普及を追い風に市場拡大を続け2010年までは2兆円を上回る生産金額であったが、地上波デジタルへの移行に伴う薄型テレビの特需が終わった2011年以降は急速に落ち込み、2012年は1.1兆円にまで縮小している。
産業用電子機器は、2001年の10兆円からほぼ一貫して減少傾向が続き、2012年では4兆円まで落ち込んでいる。通信機器では携帯電話の生産額が2008年頃までほぼ横ばいで推移していたが、2008年に端末料金と通話料金を分離した料金体系が導入された事で携帯電話の買換えサイクルが長期化し端末の販売数量と生産金額が大きく落ち込む事態となった。その後もスマートフォンの普及に合わせて海外企業のシェアが上昇していること、国内企業も海外のEMSなどからの端末調達を増加させていることなどが影響し、国内での携帯電話生産額は大幅に低下している。また電子計算機ではパソコンの生産金額が2008年以降大きく減少しているが、大幅な価格下落などが影響した。
電子部品デバイスについても、2008年までは10兆円規模の生産が行われていたが、2008年の金融危機、2011年の東日本大震災など外部的な要因、競争激化によるシェアダウン、円高による減少、国内の携帯電話や民生機器などの製造縮小といった要因から大きく落ち込、回復することができていない。
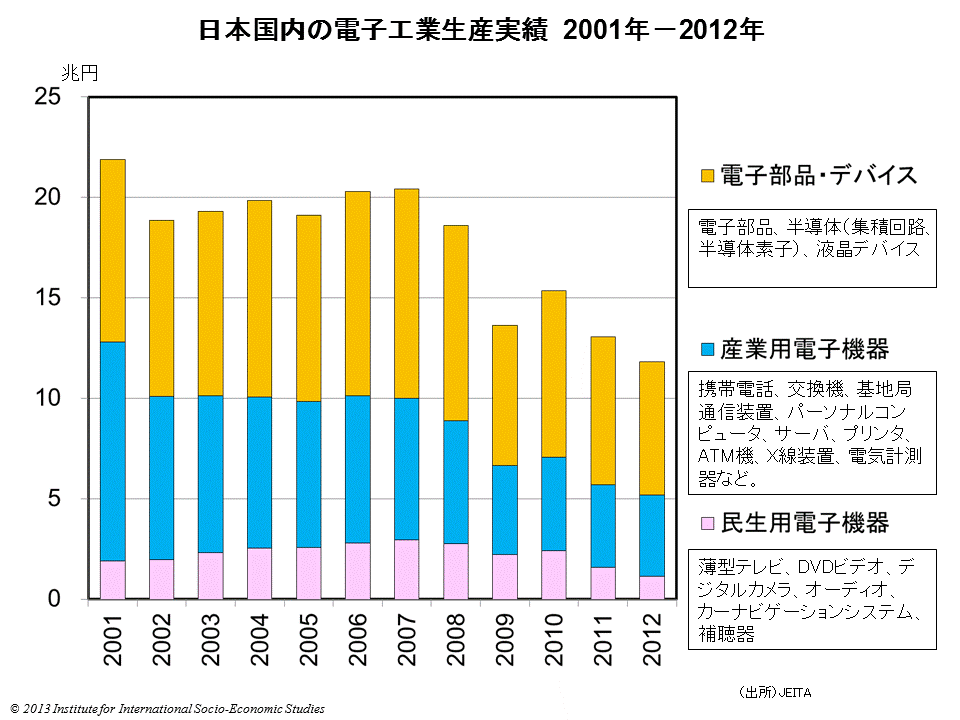
- 新しい成長分野を模索する大手電機各社
前述のように日本のエレクトロニクス生産は縮小傾向にあり、大手電機企業の売上高も伸びず業績の水準がなかなか上がらないのが現状だが、そうした中で各社は今後の成長に向けた取り組みをどのように進めているのか。
下表に主な注力分野と各社の取り組み状況をまとめているが、主に①ITサービスの分野:クラウドコンピューティング、ビッグデータ、スマート化など、②社会インフラの分野:再生可能エネルギー(太陽光発電、風力発電)、蓄電技術、新興国での火力発電、原子力発電、③ヘルスケアの分野、④消費者向け製品:スマートフォン、タブレット端末、の4分野を注力領域としている模様だ。
1番目のITサービスの分野では、特にインターネットの普及などを背景に増加した巨大なデータ群:ビッグデータを活用して新しい付加価値を生み出すサービスや、ユーザーが自らのコンピュータでなくインターネット上におかれたコンピュータリソースをサービスとして利用するクラウドコンピューティングシステムの開発などが進められている。
2番目の社会インフラの分野はこれまで比較的収益が安定していることから、多くの電機企業が取り組みを強化している。中心となる電力関連では新興国における原子力発電、火力発電システムの拡販が進められているほか、化石燃料の価格高騰や東日本大震災による福島の原子力発電所事故を背景に需要が高まっている再生可能エネルギーでは主に太陽光発電システムを中心とした事業拡大が進められている。また発電だけでなく送配電の分野でも余剰電力を蓄える蓄電池の事業や、電力利用量をモニターし発送配電を最適な状況に制御するスマートグリッドなどへの取り組みも進められている。
電力以外の社会インフラ分野では、水、交通、住宅など様々な分野でセンサーを活用して情報を収集し、その情報に基づいて適切な制御を行うスマート化の流れが進められている。
3番目のヘルスケアの分野では従来のMRIやCTスキャンといった医療検査機器に加えて、身体に取り付けたセンサーでバイタルデータを取り出して治療・予防に役立てるといった分野での取り組みが進められている。この分野は、ほとんどの企業が事業強化を進めているとみられる。
4番目の消費者向け製品では、これまで各社が積極的に取り組んできた薄型テレビ市場が飽和状態となり、新しい製品・市場創出が課題。世界的に台数増加が進むスマートフォンやタブレット端末は成長領域だが、既に韓国・米国・中国企業が市場展開で先行している。
各社の4分野への取り組みは、既存の事業ポートフォリオや独自技術などに大きく左右されるが、特に市場が大きく幅広い企業の参入が進むのは2番目の社会インフラの分野であろう。海外市場におけるニーズも強く、日本の優れた社会インフラへの関心も高い事から、海外事業拡大を狙う大手電機各社にとって非常に重要な事業分野である。ヘルスケアの分野についても高齢化の進展などから潜在的な需要は大きいと見られるが、どのような製品・サービスが受け入れられるのか各社が模索している状況であり、長期的に有望な市場という位置づけであろう。こうした成長分野への取り組みによって、各社が本格的な成長回復に向かうことを期待したい。
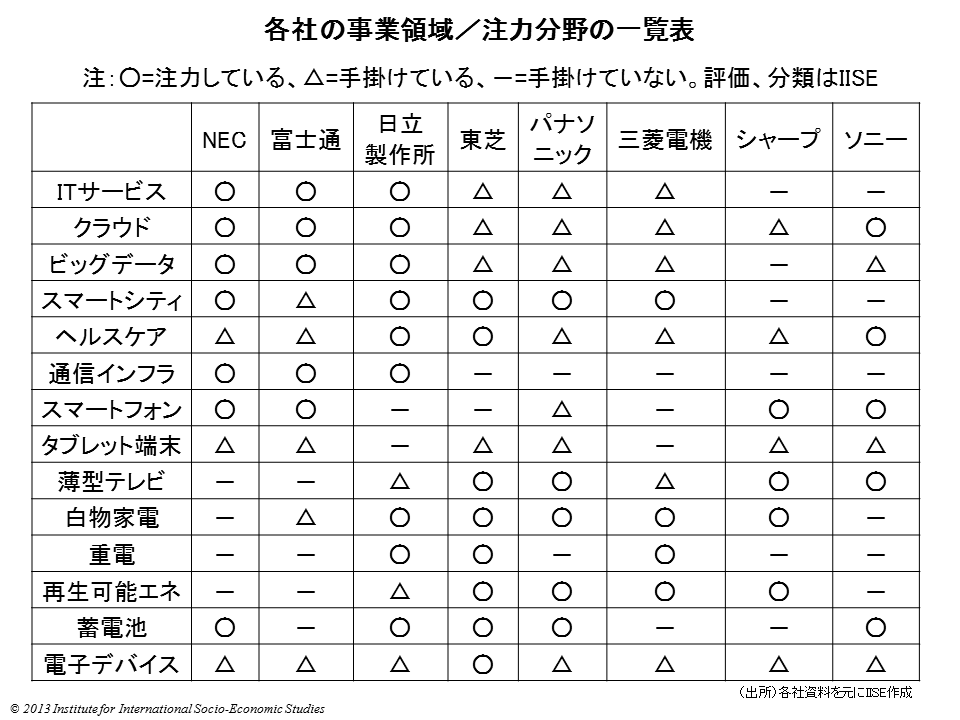
※各社の事業領域/注力分野の一覧表については、筆者が各社公表資料などを参考に独自に分類したものである。