サイト内の現在位置を表示しています。
ICT統計を創る(1)「鉱工業指数」
世界的に充実している日本の政府統計であっても、ICTに限定した統計はほとんど無い。そこで、既存の統計から工夫してオリジナルのICT統計を創る方法を紹介する。
今回は経済産業省が毎月公表している「鉱工業指数」である。
本統計、調査開始は昭和5年1月というから80年以上の歴史のある統計である。今や鉱工業産業だけで経済全体を見ることはできないが、戦前、戦後を通じて製造業中心に経済成長を続けてきた日本にとって、この統計の重要性は計り知れない。今もなお、その信頼性や速報性に優れ、最も重要な景気判断指標の1つとして多くのエコノミストに愛される指標である。
経済産業省のHPによれば、本統計の目的は「鉱工業製品を生産する国内の事業所における生産、出荷、在庫に係る諸活動、製造工業の設備の稼働状況、各種設備の生産能力の動向、生産の先行き2ヶ月の予測の把握を行うもの」とある。したがって、本統計では鉱工業製品に関する生産、出荷、在庫、稼働率等の動きが分かる。また、業種別、財別、品目別にも公表されているので、様々な鉱工業製品の中からICT関連製品だけをピックアップすることができる。
ただし、本統計は数量ベースの指数統計なので、金額ベースでICTを見ることはできない。また、指数作成の基準年が現在は2005年であることにも注意が必要である。ライフサイクルの短い品目も計上され続ける反面、最新の品目は統計に反映されない。本統計は5年に1度、採用品目の入れ替えやウエイトの見直しを行っている。次回基準年は2010年で公表されるのは2013年春頃になる予定である。
さて、先ずは品目別の統計からICT関連製品のピックアップをしてみる。本統計には生産・出荷で496品目、在庫で358品目もある。経済産業省はICT関連製品を定義していないので、目的に応じてユーザーが勝手に定義すれば良いのだが、これはこれで難儀である。今やネットで接続されている製品は多岐にわたっており、薄型テレビ等のデジタル家電だけでなく、今や白物家電だってICT製品と言えないこともない。
しかし、ここでは従来型の情報通信機能がメインである端末や情報通信インフラを支える電子計算機や通信機械のみをICT製品とし、更にICT製品の部材である電子部品・電子デバイス等のICT部品を加えてICT関連品目とした。
図表1は、本稿でピックアップしたICT関連38品目の一覧である。各品目の右側にある数字は全体に占めるウエイト。つまり、鉱工業全体を10000とした時のICT関連品目のシェアである。生産の合計で996.3。ICT全体の動きを見たい時は、この996.3をベースに各ICT関連品目のウエイトを変更して合成すれば、他業種と比較可能なICT関連品目の生産指数(以下、ICT生産指数)の完成である。
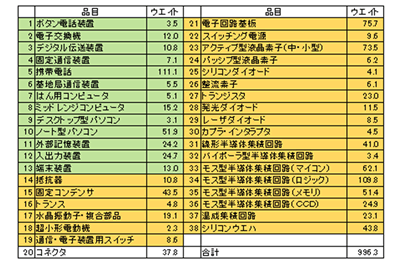
- ※(注}緑色部分がICT製品、橙色部分がICT部品、(資料}経済産業省「鉱工業指数」よりIISE作成
では、図表2で早速ICT生産指数の動きを見てみよう。なお、本統計には季節調整値と原数値と2種類あるが、方向感とレベル感を同時に見る際には月毎のブレを調整した前者の方が向いている。下記図表は1993年1月以降の生産の動きである。ICT指数は中期的には2007年12月をピークに下降トレンドが続いていることが分かる。足下の水準は2008年のリーマンショック後の落ち込み程ではないものの、ここ数年来ではかなりの低水準で推移していることも分かる。
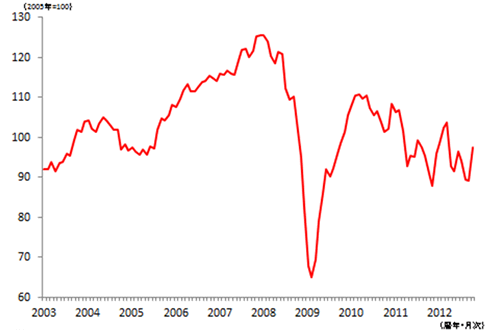
- ※(注)季節調整値、(資料)経済産業省「鉱工業指数」よりIISE作成
次に、図表3でICT生産指数をICT製品とICT部品に分けて見てみよう。比較すると、ICT製品が一貫して下降トレンドが続いているのに比べ、ICT部品はリーマンショック前まで上昇トレンドが続き、その後大きく落ち込みながらも何とか持ち直し、2011年以降は下降トレンドとなっている。
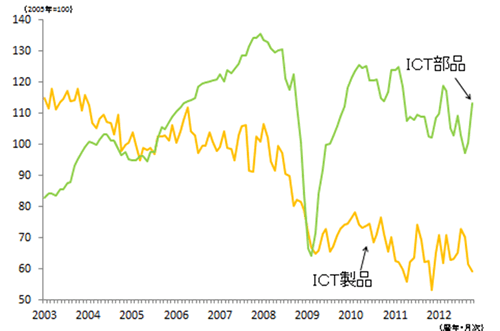
- ※(注)季節調整値。ICT製品とICT部品については図表1を参照されたい、(資料)経済産業省「鉱工業指数」よりIISE作成
更に、図表4で他の業種と比較してみよう。ここでは、日本の製造業を牽引する輸送機械と比較してみる。上下の差はあれ、両業種とも大きなトレンドは同じように見える。ただし、2011年3月の東日本大震災に伴うサプライチェーン寸断の影響は、ICTは輸送機械程に大きな影響をもたらさなかったこと、その後のエコカー補助金による上下のブレがあった輸送機械に対し、ICTは比較的安定していたこと等が分かる。
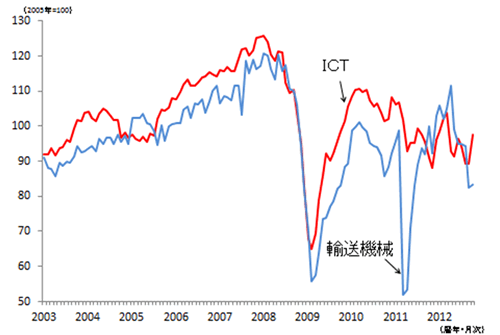
- ※(注)季節調整値、(資料)経済産業省「鉱工業指数」よりIISE作成
参考:本稿で紹介した経済産業省「鉱工業指数」は以下のURLからアクセスできる。