サイト内の現在位置を表示しています。
ICT産業はデフレの元凶か?
ICT市場調査部 部長兼主幹研究員 松島 宏和
昨年末の政権交代後、デフレ脱却は当面の日本経済において最大の目標のひとつとして一般に認識されつつある。名目ならびに実質GDPの有意な成長(多くの識者が指摘する通り、筆者も2-3%/年をイメージしている)が継続し、それに伴い賃金上昇、需要増加の結果緩やかな物価上昇期待が形成されるのならば、そのような状況が実現するのにたとえ数年かかろうともそれは歓迎すべき展開であろう。
一方、ICT産業が提供する製品・サービスは継続的に価格が低下するもの、という認識をされていらっしゃる一般の方はきっと多いのではないか。「アベノミクス」によってこの傾向に歯止めがかかるのかどうか、という問題がここで出てくるのだが、本稿では少し視点を変えて、ICT産業を含む電機産業が提供している財・サービスの過去物価推移を冷静に追いかけてみることにする。
財・サービスの物価統計として一般に広く認知されているのは、
①消費者物価指数(総務省)
②企業物価指数(日本銀行)
③企業向けサービス価格指数(日本銀行)
の3つである。この他に製造業部門別投入・産出物価指数(日本銀行)もあるが、これについては本稿ではなく別の機会に研究・考察してみたい。
まず①であるが、同指数が捕捉対象としている主要なICT関連製品はPCと携帯電話であって、これらを含む製品群(ここでは「ICTハード」と呼称する)が消費者物価全体に占めるウェイトは1%弱(92/10000)である。この他に、消費者向けの電化製品として白物家電を中心とした製品群(「白物家電」。ウェイトは107/10000)、テレビやビデオレコーダーを中心とした製品群(「AV・カーエレ」。同・139/10000)がある。これらの物価指数の前年比と、消費者物価全体に対する押し上げ/押し下げ効果(寄与度)を示したのが図1である。
2006年以降、消費者物価全体の伸び率はほぼゼロ近傍で推移している一方、「ICTハード」「白物家電」「AV・カーエレ」の3製品群はいずれも大幅な価格下落基調が継続しており、特にICTハードとAV・カーエレの下落率は突出している(グラフ左)。ただし、ここで気をつけなくてはいけないのは、これらの製品群は機能や品質が改善された新製品が続々と店頭に並ぶことが多く、ライフサイクルも短期化しているため、物価指数の算出に際しては機能・品質の改善度を考慮した「品質調整」が施されているケースが多いという点である。品質調整効果の寄与については日本銀行などが一部データを公表しているが、その寄与分析や評価を行うのは本稿の目的ではないのでここでは言及しない。しかし、品質調整の効果によって店頭における見かけの販売価格よりも統計上の物価指数の下落率が大きいことには注意が必要だ。これは、後述する企業物価や企業向けサービス価格についても程度の差こそあれあてはまる。
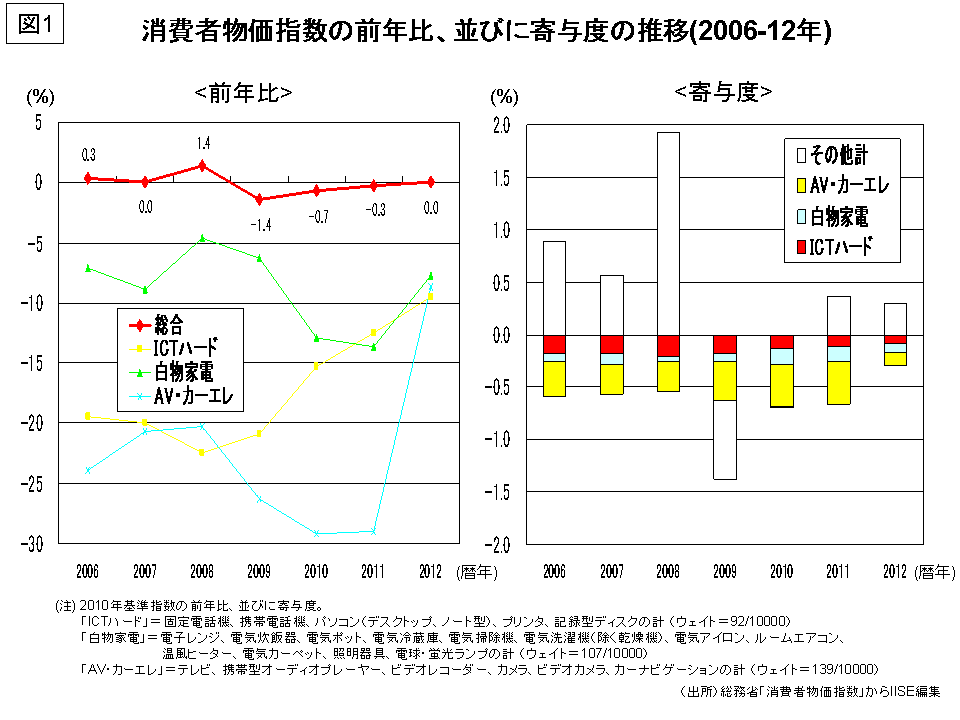
一方、これら3製品群が消費者物価全体をどれだけ押し下げているかをみたのがグラフ右である。3製品群合計では継続して約0.5~0.7%ポイント消費者物価を毎年押し下げており、うちICTハード単独では約0.1~0.2%ポイントの押し下げ寄与である。
これを「大きい」とみるか、「大したことがない」とみるか。現在の日銀の消費者物価上昇率目標は2%であるから、電機関連製品の合計でその絶対値の1/4を超える寄与がある、というのは十分大きいとみるのが一般消費者の感覚からすると妥当だろうか。
しかし一方で注目すべきは、2012年の物価下落率は3製品群とも1ケタにとどまり、これによって3製品群計の押し下げ寄与が0.3%ポイント程度にまで縮小したことである。これも2通りの解釈が可能である。
a. 店頭販売価格の下げが小さくなったので、デフレ体質から少し脱出の気配が出てきた
b. 製品供給者側の品質向上ペースに翳りがみえてきた
もしa.の解釈ならば、同製品群に対する消費者の物価下落期待が少し緩みマクロ環境の将来的な改善を示唆するものとなる。しかし、白物家電とAV・カーエレに関しては2012年にそれぞれエアコンとテレビにおける価格調査対象品目の入れ替えによる物価下落率縮小(すなわち統計上のトリック)が寄与している可能性が高く、2013年にこの要因が剥落すると再度物価が下落する懸念が残る。
一方、b.の解釈ならばベンダー側の技術進歩が停滞している可能性を示す全く別の解釈となる。どちらが正しいのか(あるいは両者が複合したものか)の検証は現時点では難しいが、2013年以降もこの傾向が続くようならば「トレンドが変わった」可能性はある。
次に②であるが、国内企業物価全体でみると中長期的に明確な「デフレ」の傾向があるわけではない(図2)。しかし、電気機器、電子部品・デバイス、情報通信機器はいずれも物価の下落傾向が常態化しており、特に情報通信機器は著しい。上記3製品群が国内企業物価指数全体に占めるウェイトは合計で12%強であるが、全体への物価下落寄与は0.4~1.0%ポイント/年であり、ほぼ恒常的な下押し要因となっていることがわかる。ただし消費者物価の場合と異なり、2012年に下落率並びに同寄与が縮小したという兆候はない。
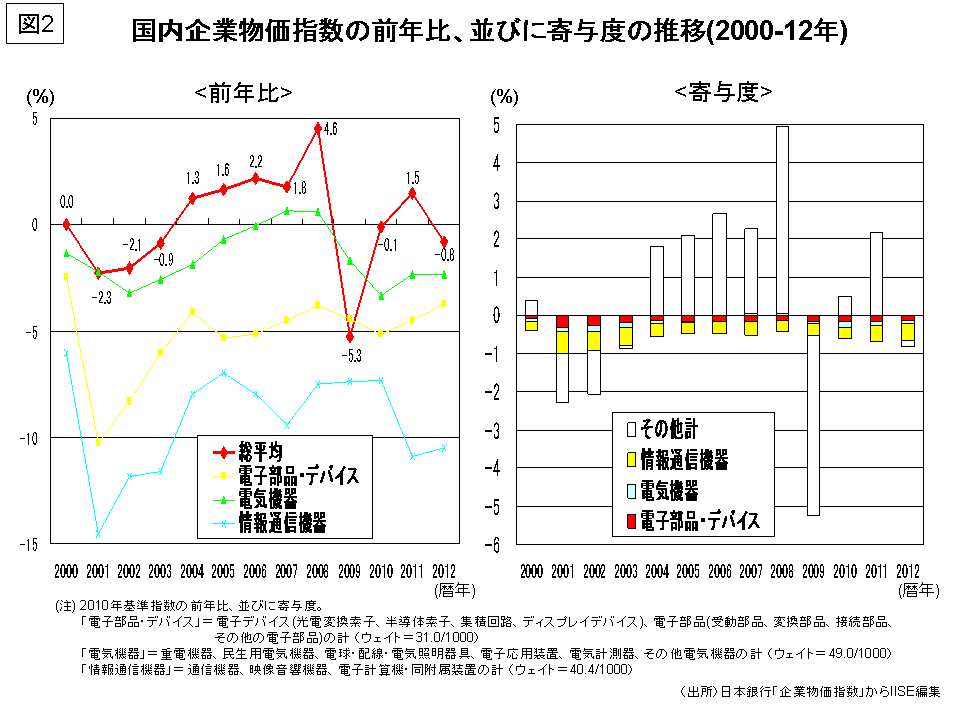
最後に③であるが、企業向けサービス価格全体は景気の動きとの連動性がかなり高く、過去10年強の数字をみると全体としては若干の下落傾向が見てとれる。そして、そのうち13%弱のウェイトを持つ情報サービスはこれとほぼ連動した動きとなっている(総平均より情報サービスの方が必ずしも下落率が高いというわけではない)。つまり、情報サービスが他のサービス部門と比較してデフレに特別に寄与しているという傾向は見当たらない(図3)。
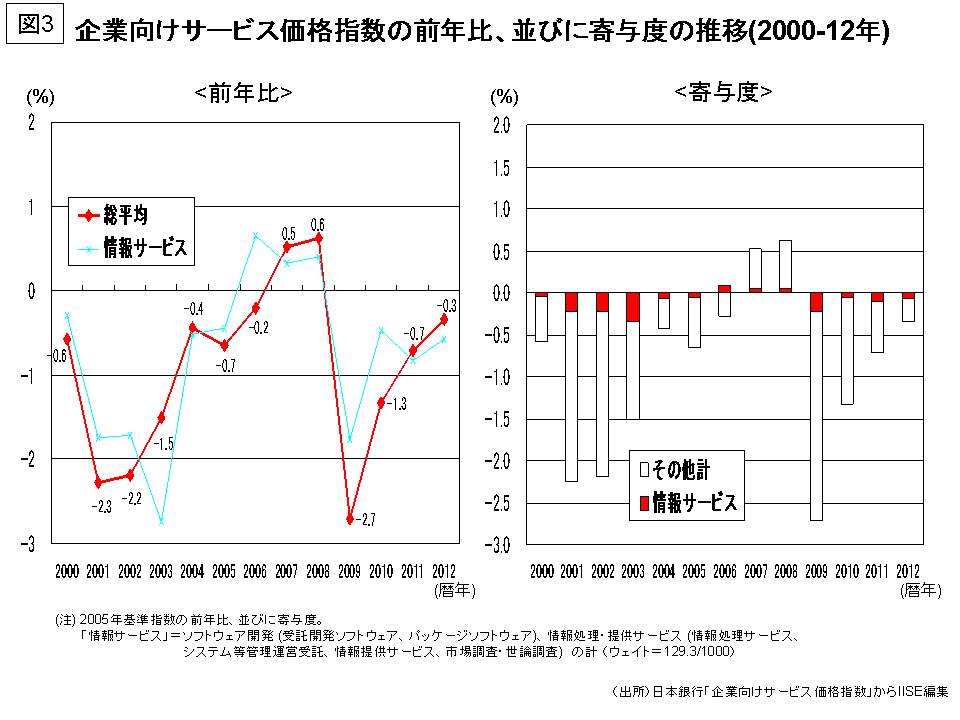
これら3つの物価指数の推移・比較を簡単に総括すると、以下のようになろう。
-
(1)ICT産業を含む電機産業が提供している財・サービスは、サービスにおいては国全体の推移に連動した価格変化をたどっておりデフレに特別の寄与をしてはいないが、財においては消費者向け、企業向けともに明らかな下押し要因として寄与している。
-
(2)電機産業が提供している財の中では、物価下落率が比較的小さいのは重電機器や白物家電等の民生用電気機器であり、比較的大きいのは電子部品・デバイスや情報通信機器である。
-
(3)電機産業が提供している財・サービスには多かれ少なかれ「品質調整」による物価下落効果があり、これがそれぞれ一定の寄与をしている。
-
(4)特に消費者物価においては、全体の伸び率がゼロ近傍で推移している中で電機関連製品が有意な下押し寄与をしており、電機関連製品の価格下落がデフレの一要因であるという一般消費者の印象を裏づけしている。
筆者が特に気にかかるのは(2)と(4)の動向とその原因である。一般によく指摘されるのは、電子部品・デバイスや情報通信機器はいわゆるグローバルプロダクトであり、ベンダー間の国際競争、技術競争が激しいから品質調整込みの価格低下傾向に歯止めがかからない、というものである。だとしたら、程度の差はあるかもしれないがどの国でも電子部品・デバイスや情報通信機器は物価の下押し効果をもたらすはずであり、日本以外の他国において「デフレ」の傾向は生じていないという現実からすると「ICT製品がデフレの主要因」と短絡的に結びつけてしまうのには無理があろう。やはり日本の場合、需給関係の緩み、低成長の継続といったマクロ環境要因によって物価上昇率が低いことが常態化しており、それにICT製品という個別要因が加わっている、と理解するのが自然とみられる。
裏を返せば、デフレ状態が解消したからといってICT製品の価格低下に歯止めがかかるとは必ずしもいえないことになる。これを「業界の特殊性」として片付けてしまうことは簡単であるが、ICT産業、電機産業が抱える最大の構造的特性のひとつとしてまだまだ研究・調査が必要な分野であることは間違いない。