サイト内の現在位置を表示しています。
IISEシンポジウム「人口減少・多死社会に対応したデジタルヘルス」開催報告
2025年3月24日
今年度のIISEシンポジウムは、会場とオンラインをあわせて約100名の参加者の皆様と開催させていただき、ご登壇者の素晴らしいご講演に加え、参加者からの積極的なご質問もあり、充実した議論を行うことができました。また、会場参加においては、休憩時間を登壇者、参加者、アクセシビリティ研究会メンバーとのネットワーキングの時間とさせていただき、コーヒーやお菓子を楽しみながら、さらなる議論を行う楽しい時間となりました。
IISEでは、様々な関係機関や有識者等との知的交流を通じて「知の集積」を図り、リサーチをベースに、デジタルでの社会課題解決の未来の姿をThought Leadership活動を通じて発信しております。弊社理事長の藤沢久美からは、開会のご挨拶として、このシンポジウムがご参加の皆様と一緒に未来を考えるきっかけになることへの期待が述べられました。
基調講演は、今年度から弊社の理事に招聘された大島一博から「人口減少社会の迎え方」(大島のプレゼン資料はこちらをクリックください)と題し、わが国の人口構造の推移からヘルスケア分野が抱える課題などの全体像を提示し、この分野でデジタルに関する研究や実用化が進むことの必要性について言及しました。人口減少・多死社会という大きな課題を乗り越えるためには、今、アクションを起こし始めるタイミングであり、分野や階層を超えた総力戦で臨んでいくべきであるとのお話しは、この後の講演プログラムへの流れにつながるものとなりました。

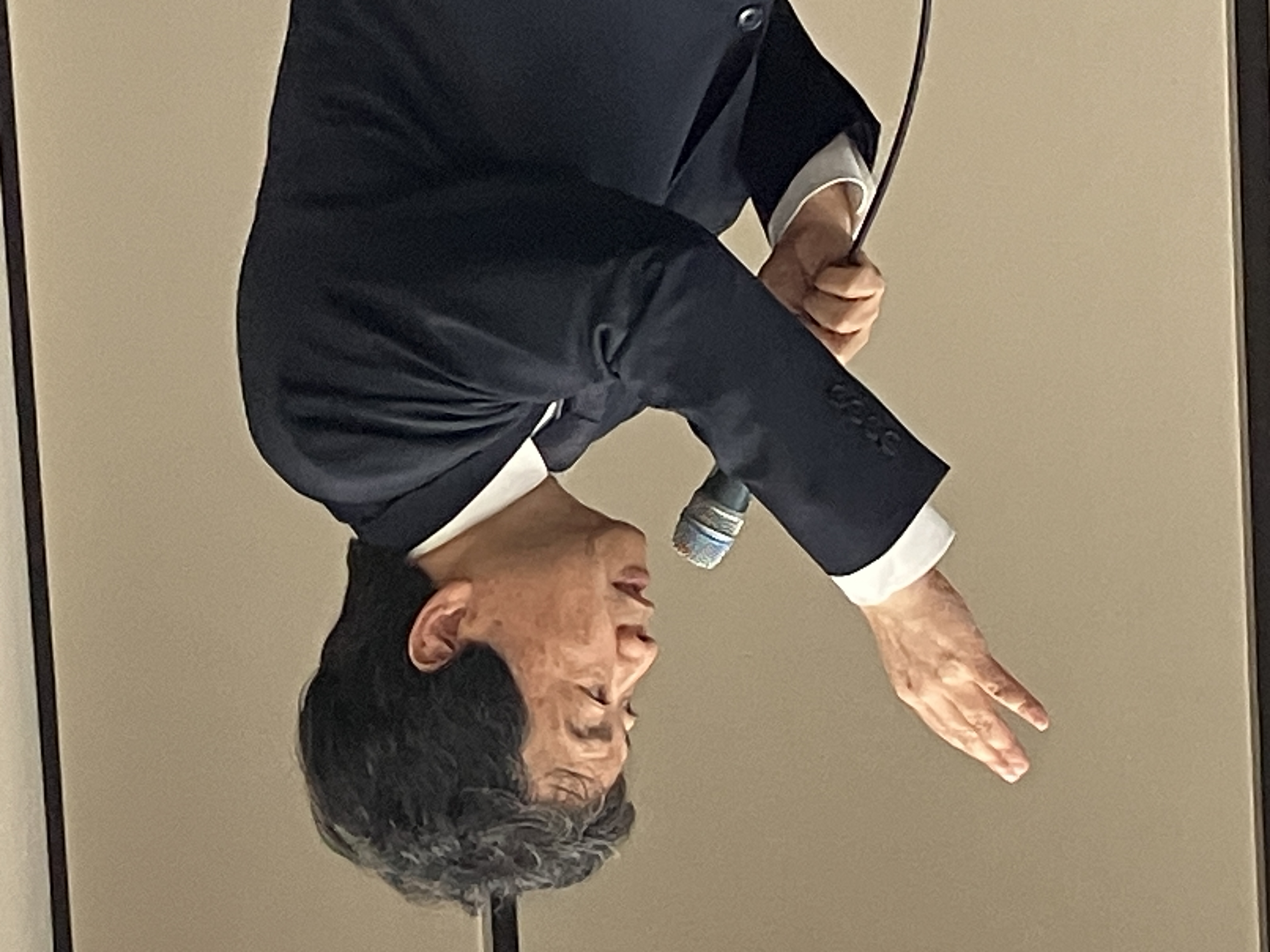
弊社理事 大島の基調講演
講演1は、東京医療保健大学東が丘看護学部看護学科/大学院看護学研究科の中島美津子教授から「少子化による看護職不足と業務のリエンジニアリングの必要性」(中島氏のプレゼン資料はこちらをクリックください)と題し、医療従事者の中で最大の人口を占める看護職の働き方改革についてお話しいただきました。中島先生は、大学で教鞭をとられる前は、病院で看護部長や副院長なども歴任されており、臨床現場での看護師のリアルな実態を踏まえて、データを活用して業務を見える化をしていくことの重要性を指摘されました。看護職こそ研究が必要であり、アカデミックだけでなく産業界ともどんどんと協働していくべきとのご発言は、力強いメッセージとなりました。
続いては、講演2としてケアプロ株式会社 川添高志社長より「ヘルスケア分野の働き方改革と離職防止」(川添氏のプレゼン資料はこちらをクリックください)と題し、ケアプロの訪問看護で実践されているデジタルの活用について具体的なお取り組みをご紹介いただきました。デジタル活用などを含め働く環境を整備することで、若い看護師も入社されてきており、新卒の看護師であっても、2年間をかけて訪問看護師として一人前にしていく教育プログラムも開発されているとのことでした。医療機関で働くだけでなく、ケアの必要な児童の修学旅行への付き添いやスポーツイベントの支援など看護師資格があるからこそできる仕事の幅を広げ、隙間時間で働けるようなマッチングアプリの活用など働き方改革につながる実践例はとても参考になりました。また、東京女子医大では顧問として看護職の離職防止に取り組んでいらっしゃるということで、現在進行形のお話もお伺いすることができました。

東京医療保健大学 中島教授
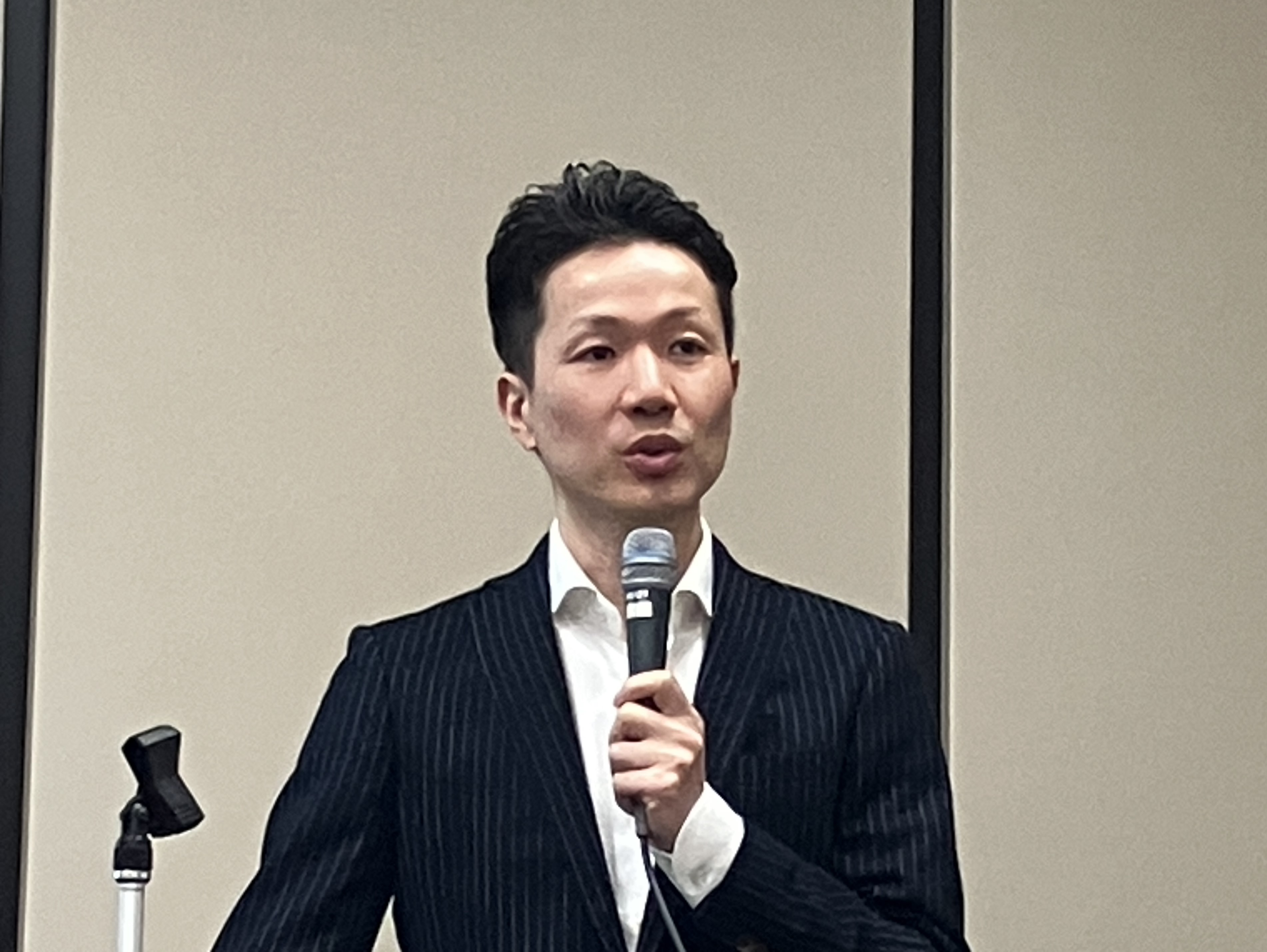
ケアプロ株式会社 川添社長
休憩を挟み、後半は、海外での取り組みを中心としたプログラムであり、弊社主幹研究員の遊間和子から「英国・オランダにおけるヘルスケアデータの活用とQOD向上」(遊間のプレゼン資料はこちらをクリックください)が報告されました。英国のNHSイングランドは、人手不足とサービスの質向上のため急速にデジタル化を進めており、医療だけでなく、社会福祉サービスとの間でもデータ交換ができるように変わってきています。QODに関しても、2008年に終末期に関する国家戦略が策定され、人生最終段階における本人の希望をデジタルで共有するシステムEpaCCsが地域ごとに構築されており、ロンドン地域のUCPの取り組みが紹介されました。オランダは、PHRの構築に注力しており、MedmijというPHRのためのデータ交換の仕組みを介して、安楽死などの終末期の希望についてのデータも共有できるようになってきています。また、英国の「NHS CIS2」やオランダの「Dezi」といったフレキシブルで低コストな医療・介護従事者向けデジタルIDの開発の必要性も訴えました。
続いて、日本・エストニアEUデジタルソサエティ推進協議会の牟田学理事からは「エストニアにおける死亡情報のワンストップサービス」(牟田氏のプレゼン資料はこちらをクリックください)と題し、世界でも有数のデジタル先進国であるエストニアの取り組みについてご紹介いただきました。エストニアのXロードでは、どのシステムからもマスターデータとなるデータベースがリアルタイムで更新される仕組みであり、自動化することで人間側が処理する作業をできるだけ少なくしています。死亡情報においても、病院からの通知で人口登録データベースが更新され、年金や各種手当の停止や相続の手続きも自動で行われるとのことで、日本の状況との大きな格差に驚かされることとなりました。エストニアのデジタル化の進展は、国民が政府を信頼していないからこそ、透明性の高い仕組みが必要ということで発展したというお話しは、日本のDXのあり方を根本から考え直すものとなりました。

弊社調査研究部 遊間
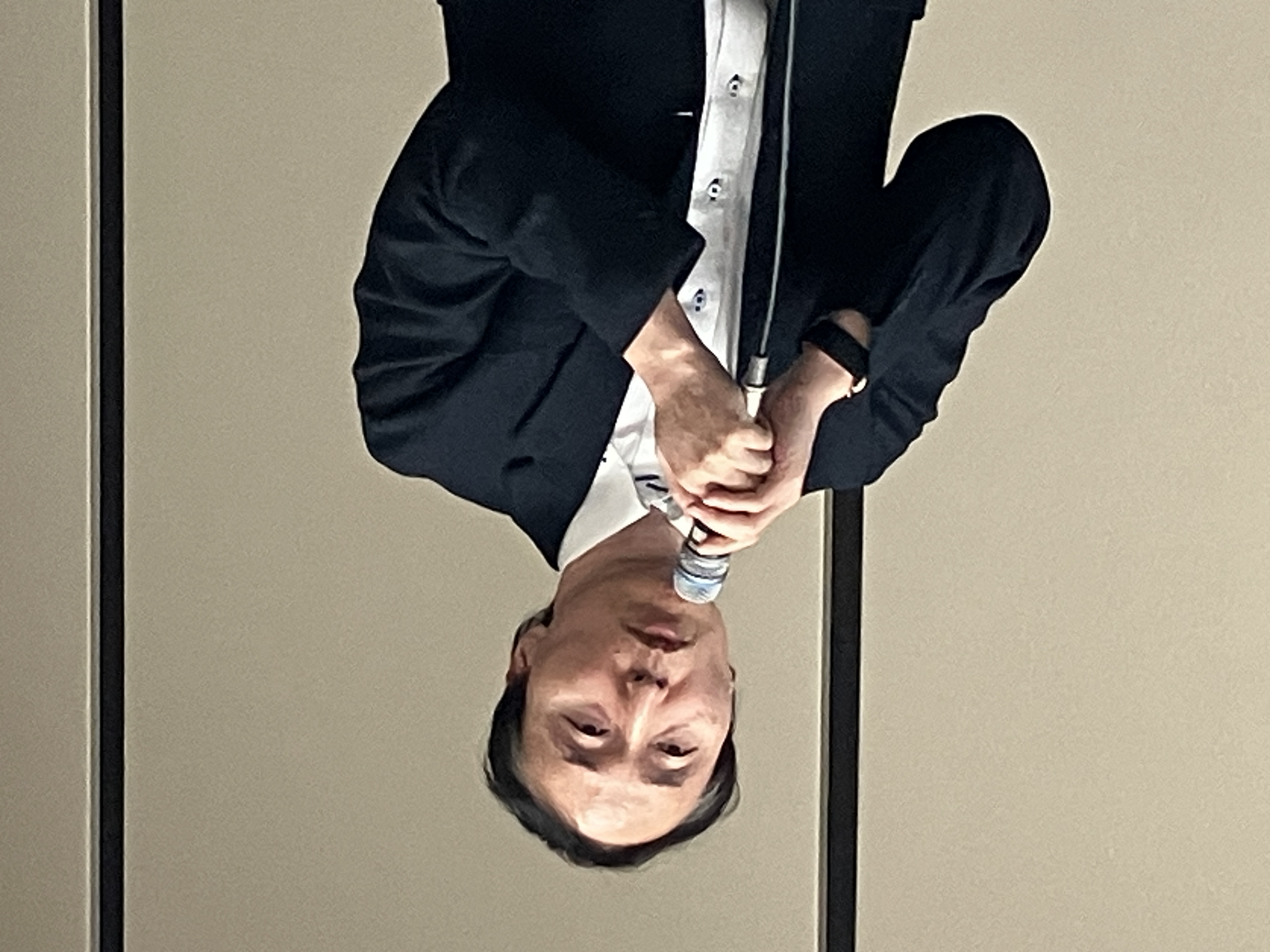
JEEADiS 牟田理事
最後に、アクセシビリティ研究会の主査でもある東洋大学名誉教授の山田肇氏から、「アクセシビリティ研究会による調査研究のご紹介とまとめ」(山田氏のプレゼン資料はこちらをクリックください)と題し、研究会で作成中の調査研究報告書についてご紹介させていただきました。
閉会にあたり、弊社理事の谷川浩也より本日のシンポジウムの所感と御礼のご挨拶をさせていただき、盛会にシンポジウムを終えることができました。
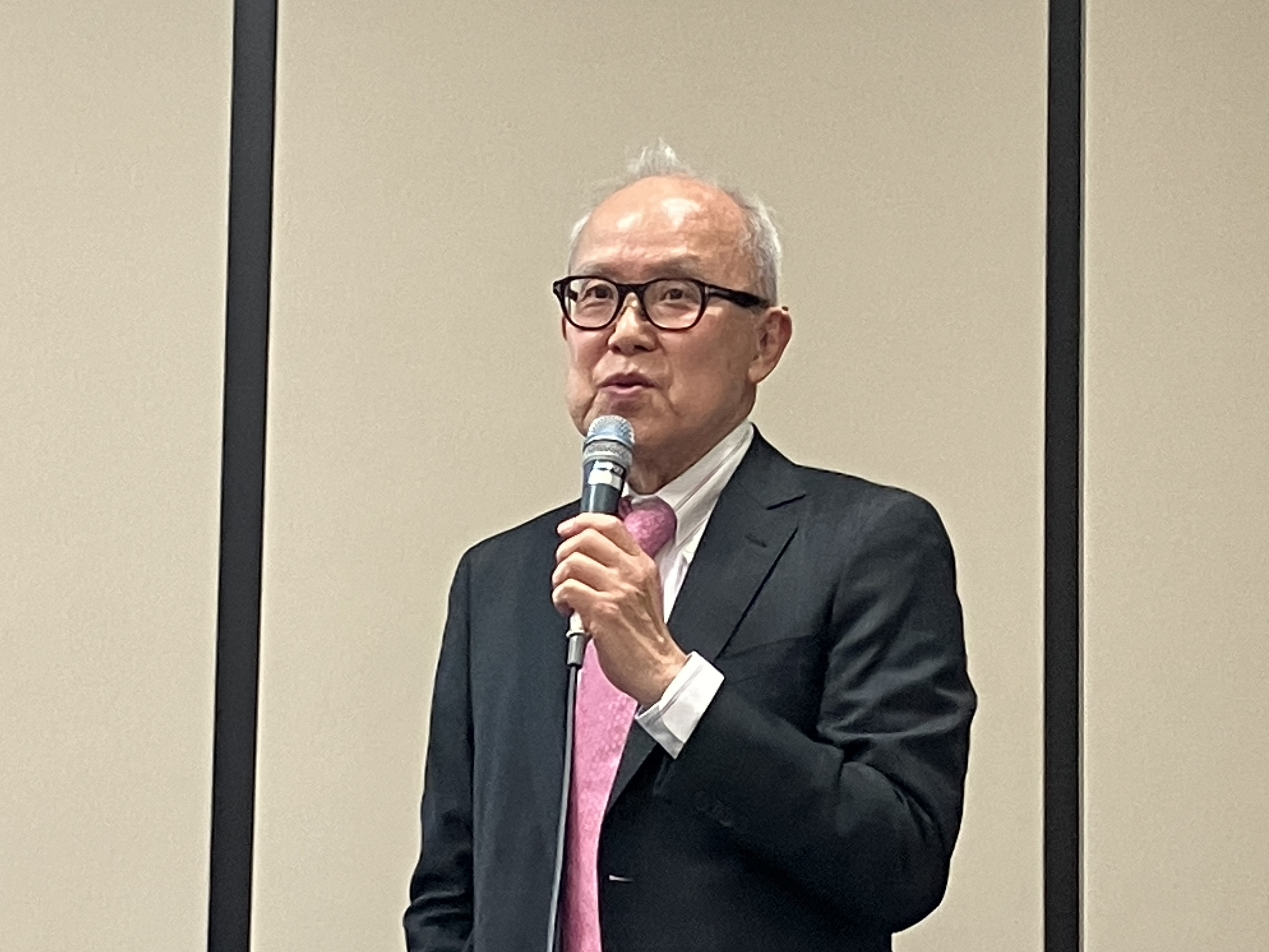
東洋大学 山田教授

弊社理事 谷川からの閉会のご挨拶
スピーカーとプログラム
| 13:30 | ご挨拶 | 株式会社国際社会経済研究所 理事長 藤沢 久美 |
| 13:35 | 基調講演 「人口減少社会の迎え方」 |
大島 一博 |
| 14:15 | 講演1 「少子化による看護職不足と業務のリエンジニアリングの必要性」 |
中島 美津子 |
| 14:45 | 講演2 「ヘルスケア分野の働き方改革と離職防止」 |
川添 高志 |
| (15:15-15:40 休憩/会場でのネットワーキング) | ||
| 15:40 | 講演3 「英国・オランダにおけるヘルスケアデータの活用とQOD向上」 |
遊間 和子 |
| 16:10 | 講演4 「エストニアにおける死亡情報のワンストップサービス」 |
牟田 学 日本・エストニアEUデジタルソサエティ推進協議会 理事 |
| 16:40 | アクセシビリティ研究会による調査研究のご紹介とまとめ | 山田 肇 東洋大学 名誉教授/アクセシビリティ研究会主査 |
| 16:55 | 閉会 | 株式会社国際社会経済研究所 理事 谷川 浩也 |